アルコールチェック義務化の全知識|検知器の選び方から記録方法まで

Cariot活用による事故の防止と削減
交通事故を未然に防ぐには、どのような事故発生リスクがあるかを把握した上で、ドライバーへの適切な教育・指導を行う必要があります。
Cariotを活用した安全運転管理によって車両事故を防ぐ取り組みをご紹介します。
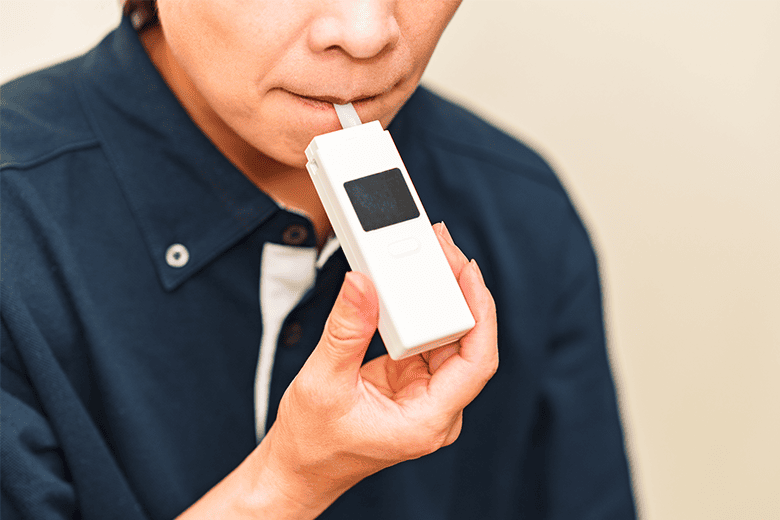
こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。
2023年12月1日より、道路交通法の改正に伴い、アルコール検知器を用いたアルコールチェックが白ナンバーの自動車を保有する多くの企業で義務化されました。
この規制は、飲酒運転による重大事故を未然に防ぐことを目的としており、企業にとって安全管理と法令遵守の両面で重要な取り組みとなっています。
本記事では、アルコールチェック義務化の最新情報(2025年時点)を基に、対象企業の条件や検知器の選び方、記録方法、費用、デジタル化対応まで、網羅的に解説します。自社の安全運転管理体制を強化し、効率的かつ確実に法令対応を進めるための実践的なガイドとしてご活用ください。
1.アルコールチェック義務化の現状と重要性
2025年現在、アルコールチェックの義務化は多くの企業にとって必須の取り組みとなっています。道路交通法の改正により、これまで緑ナンバー車両(事業用車両)に限定されていたアルコールチェックが、白ナンバー車両へのアルコールチェックとして一般企業の社用車にも拡大されました。
この義務化の背景には、飲酒運転による重大事故の防止があります。2021年の千葉県八街市などで起きた重大事故を背景に、飲酒運転撲滅への取り組みが一層強化されています。
参考:安全運転管理者による運転者に対する点呼等の実施及び酒気帯び確認等について(通達)【警察庁】
アルコールチェック義務化の基本知識
段階的な施行スケジュール
アルコールチェックの義務化は、二段階に分けて施行されました。
| 施行時期 | 義務化内容 |
|---|---|
| 2022年4月1日 | ・目視等による酒気帯びの有無の確認 ・確認結果の記録と1年間保存 |
| 2023年12月1日 | ・アルコール検知器を用いた確認の義務化 ・検知器の常時有効保持 |
この義務化は、道路交通法施行規則の改正に基づいており、具体的には以下の条文で規定されています。
- 道路交通法施行規則第9条の10の6(酒気帯び確認)
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。 - 道路交通法施行規則第9条の10の7(記録保存)
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
引用:道路交通法施行規則【e-GOV法令検索】
2.対象企業の条件
白ナンバー車両の対象条件
白ナンバーでアルコールチェックの対象となる企業は、以下のいずれかの条件を満たす事業所です。
- 乗車定員11人以上の白ナンバー車両1台以上を保有する場合
- 白ナンバー車両を5台以上保有する場合(自動二輪車は1台を0.5台として計算)
対象となる車両は、社用車・営業車のほか、レンタカー、自家用車を問わず、その車両を業務で使用するかどうかです。従業員の自家用車を業務で使用する場合も対象となりますので注意しましょう。
3.安全運転管理者の役割と罰則
安全運転管理者の選任義務
対象企業は、各事業所に安全運転管理者を選任する必要があります。選任基準は以下のとおりです。
- 年齢:20歳以上(副安全運転管理者が置かれている場合は30歳以上)
- 運転経験:2年以上(自動車管理に関し公安委員会が行う教習を修了している場合は1年以上)
- 欠格事由がないこと
強化された罰則
安全運転管理者に関する罰則は2022年10月1日より大幅に強化されました。
| 違反内容 | 改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 安全運転管理者 選任・解任義務違反 |
5万円以下の罰金 | 50万円以下の罰金 |
| 安全運転管理者 選任・解任届出義務違反 |
2万円以下の罰金 | 5万円以下の罰金 |
| (新設)是正措置命令違反 | ー | 50万円以下の罰金 |
4.アルコール検知器の選び方
検知方式の比較
アルコール検知器の選び方で最も重要なのが検知方式です。
アルコール検知器には主に半導体式と電気化学式(燃料電池式)の2つの方式があります。
| 項目 | 半導体式 | 電気化学式(燃料電池式) |
|---|---|---|
| 価格相場 | 3,000~12,000円 | 15,000~50,000円 |
| 精度 | 普通 | 高精度 |
| 測定時間 | 短い(約5秒) | やや長い(約10〜15秒) |
| 誤検知リスク | やや高い | 低い |
| 使用回数上限 | 1,000~5,000回 | 10,000~50,000回 |
※価格や使用回数など製品により異なるので、販売店での仕様の確認を推奨します。
測定方式の種類
測定方式にも、以下の3種類があります。
- 吹きかけ式:最も手軽だが、周囲環境の影響を受けやすい
- ストロー式:精度が高く、複数人での使用が可能
- マウスピース式:最も精度が高いが、衛生管理が必要
推奨製品の特徴
法人向けには以下の特徴を持つ製品がおすすめです。
- アルコール検知器協議会の認定品
- 電気化学式センサー搭載
- Bluetooth連動機能
- 写真・動画等の撮影機能(なりすまし防止)
- 検知データ自動記録機能
5.記録方法
アルコールチェックの記録は、法令で定められた8つの項目を必ず記録する必要があります。
- 確認者名:チェックをする者の氏名
- 運転者名:チェックを受ける運転者の氏名
- 車両情報:車両登録番号または識別記号
- 確認日時:確認の年月日と時刻
- 確認方法:アルコール検知器使用の有無、対面確認の方法
- 酒気帯びの有無:検知結果
- 指示事項:必要に応じて記載
- その他必要事項:特記すべき事項
記録は1年間の保存が義務付けられていますが、保存方法の形式は決まっておらず、紙の保存でも電子保存でも問題ありません。
しかし、紙での記録は、特にドライバーや車両が多い事業所の場合には誤記入の可能性もあり、すぐに保管場所が問題になることが考えられます。
よって、正確で効率的な方法としては、専用のアプリやシステムでの記録が適しているでしょう。
6.実施方法
アルコールチェックは、運転前と運転後の2回実施することが基本です。
アルコールチェックの方法は対面が原則ですが、直行直帰の場合や、早朝・深夜の乗車時など、対面での確認が困難な場合にはこれに準ずる方法で実施することができます。
具体的には、運転者に携帯型アルコール検知器を携行させるなどした上で、
- カメラ、モニター等によって、安全運転管理者が運転者の顔色、応答の声の調子等とともに、アルコール検知器による測定結果を確認する方法
- 携帯電話、業務無線その他の運転者と直接対話できる方法によって、安全運転管理者が運転者の応答の声の調子等を確認するとともに、アルコール検知器による測定結果を報告させる方法
等の対面による確認と同視できるような方法が考えられます。
引用:安全運転管理者の業務の拡充等 アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A【警察庁】
これを踏まえて、従業員に携帯型アルコール検知器やスマートフォンを支給し、アプリで記録できるような体制を整えておきましょう。
また、24時間対応可能な外部委託サービスもあるので、検討してみると良いかもしれません(これについては第7・8章でも少し触れます)。
7.費用について
導入費用の相場
アルコールチェックを導入するための費用は、導入する機器やシステムによって大きく異なります。
以下はアルコール検知器の種類ごとの一般的な相場になります。詳細はメーカーや販売店に確認するようにしてください。
| 項目 | 価格相場 |
|---|---|
| 半導体式検知器 | 3,000~12,000円 |
| 電気化学式検知器 | 15,000~50,000円 |
| スマホ連動型 | 20,000~80,000円 |
| 据置型システム | 100,000~300,000円 |
※メーカー、サービス提供会社、機器によって金額は異なりますので、あくまでも目安とお考えください。
こちらを見ると、価格にはかなりの幅があります。これはさまざまなメーカーが色んなものを製造・販売しているためです。「初期費用を抑えられるように、安いものが良い」と思って安易に選ぶと、誤検知が多かったり機能が足りなかったり、自社の使用方法に合わなかったりするので、注意が必要です。
また、アルコール検知器は基本的に消耗品です。アルコール検知器のセンサーの寿命は1〜1年半、または規定の使用回数です。寿命が切れると、センサー交換か製品ごと買い替える必要があります。測定方式によって、複数人で使用できなかったりもするので、その点にも注意が必要です(吹きかけ式は、衛生面の観点から複数人での使用に適しません)。
初期費用だけでの比較ではなく、アルコールチェックが必要な従業員数、チェックは一日に何回行うのか、マウスピースやストローはどのくらい必要か、なども計算し、ランニングコストとあわせて検討しましょう。
| 項目 | 費用相場 | 内容 |
|---|---|---|
| センサー交換 | 年額10,000円〜30,000円 | 電気化学式の場合 |
| 機器の買い替え | 年額3,000~12,000円 | 半導体式の場合 |
※メーカー、機器によって金額は異なりますので、あくまでも目安とお考えください。
8.最新のデジタル化対応
2025年現在、アルコールチェックの効率化と正確性を高めるため、デジタル技術の活用が多くの企業で進んでいます。スマホ連携アプリ、自動化システム、外部委託サービスの導入により、法令遵守をスムーズに実現しつつ、業務負担を軽減できます。
以下では、それぞれの特徴と実務での活用方法をわかりやすく解説します。
| 項目 | 費用相場 | 内容 |
|---|---|---|
| アプリ利用料 | 月額800~3,000円/人 | クラウド管理システム |
| 外部委託 | 月額5,000~15,000円/人 | 24時間代行サービスなど 従量課金制のサービスもあり |
※サービス提供会社によって金額は異なりますので、あくまでも目安とお考えください。
スマホ連携アプリの活用
スマホ連携アプリのアルコールチェックシステムは、測定から記録までを効率化するツールとして広く採用されています。このシステムは、スマートフォンとアルコール検知器をBluetoothで連携させ、データ管理や確認作業を簡素化します。
主な機能は以下のとおりです。
- Bluetooth連携:検知器の測定結果をスマホに自動送信。手入力の手間を省き、記録ミスを防止。
- 顔写真撮影:運転者の本人確認を行い、なりすましを防止。
- GPS位置記録:測定場所を記録し、遠隔地でのチェックの信頼性を確保。
- クラウド保存:データをクラウドに自動保存。1年間の保存義務を簡単に遵守可能。
- リアルタイム通知:異常値(アルコール検知時)を即座に管理者へ通知し、迅速な対応を支援。
- 統計レポート:月次・年次の測定データを自動集計し、分析や報告書作成を効率化。
これらの機能は、直行直帰や複数拠点での運用に特に有効です。例えば、営業職が多い企業では、GPSや顔写真機能を活用して遠隔チェックの信頼性を高められます。
Cariotが提供するアルコールチェック機能では、Bluetooth連携で、スマートフォンで行ったチェック結果と撮影した顔写真が即時にクラウド上に保存されます。管理者が遠隔でチェック結果を確認でき、未実施での運転にはアラートが出るなど、必要な設定を企業ごとに登録できます。
詳しくは専用ページをご覧ください。お見積りも可能です。
自動化システムの導入
アルコールチェックの業務負担を軽減するため、他の業務システムと連携した自動化システムも普及しています。これにより、チェックと既存の業務フローを一体化し、効率的な運用が可能です。
特に、大規模企業や24時間稼働の事業所では、ERP(Enterprise Resource Planning/企業内にある人的資源や資産を統合管理することで、経営や業務の効率化・最適化を図る考え方)を検討するのも良いでしょう。
- 勤怠管理システム連携:出勤時の打刻と同時にアルコールチェックを実施。従業員のルーティンに組み込みやすく、チェック漏れを防止。
- 車両管理システム連携:車両のキー貸出時や運転開始時にチェックを行い、車両使用前の確認を確実に実施。
外部委託サービスの活用
自社でのアルコールチェックの運用が難しい場合、専門の外部委託サービスを利用することで、24時間対応や専門性の高い対応の確保が可能です。特に、早朝・深夜業務や小規模企業での導入が進んでいます。外部委託は、専門知識が不足する場合や、初期導入時の教育コストを抑えたい場合に有効です。
主なサービスと特徴は以下のとおりです。
| サービス内容 | 特徴 | 適用場面 |
|---|---|---|
| 24時間代行サービス | オペレーターがビデオ通話などで遠隔確認。 測定の信頼性を確保。 |
深夜・早朝勤務の多い運送業や警備業など |
| システム運用代行 | 記録管理やレポート作成を代行。 管理者の事務負担を大幅削減。 |
専門担当者の確保が難しい中小企業など |
| 研修・教育サービス | 安全運転管理者や従業員向けの教育を提供。 法令遵守の意識向上。 |
制度導入時や新入社員研修時など |
9.よくある質問
A. はい、対象となります。車両の所有形態に関わらず、業務で使用する場合はアルコールチェックが必要です。
Q2. 通勤時のマイカー使用は対象ですか?
A. 単純な通勤のみの場合は対象外です。ただし、車両を営業活動などの業務で使用する場合は対象となります。
Q3. アルコールチェックを忘れた場合の罰則は?
A. 直接的な罰則はありませんが、安全運転管理者の業務違反となり、是正措置命令が出される可能性があります。命令に従わない場合は50万円以下の罰金となります。
Q4. 検知器の精度チェックは必要ですか?
A. はい、必要です。定期的な校正やメンテナンスを行い、『常時有効保持』の義務を守る必要があります。
Q5. 数値が0.15mg/L未満でも運転してはいけませんか?
A. 2025年10月現在の法的には0.15mg/L未満であれば酒気帯び運転にはなりませんが、0.00mg/Lが理想です。企業として独自の基準を設けることをおすすめします。
Q6. 検知器が故障した場合はどうすればよいですか?
A. 目視等による確認は継続し、速やかに修理または代替機器を用意してください。常時有効保持の義務があるため、故障状態での使用は避けてください。
参考:安全運転管理者の業務の拡充等 アルコール検知器を用いた酒気帯び確認等に係るQ&A【警察庁】
10.まとめ
アルコールチェックの実施において、企業が取り組むべき重要なポイントをまとめます。
実施すべき対応の要点
- 対象確認:自社が義務化対象かの確認
- 管理者選任:安全運転管理者の適切な選任
- 機器導入:適切なアルコール検知器の選択・導入
- 記録体制:法定8項目の確実な記録・保存
- 実施体制:24時間対応可能な体制構築
- デジタル化:効率化のためのシステム活用
- 継続管理:機器メンテナンスと制度運用
アルコールチェック義務化への対応は、単なる法令遵守の問題ではなく、従業員の安全と企業の信頼性を守る重要な取り組みです。適切な機器選択と運用体制の構築により、効率的で確実なアルコールチェック体制を整備し、安全な事業運営を実現しましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
これからもCariotは、より便利に使っていただくための機能の開発を進めてまいります。
ご意見・ご質問・ご感想・ご要望などがございましたら、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください!
お問い合わせはこちら
※2025年現在、技術の進歩によりさまざまな支援ツールやサービスが提供されています。自社の規模や業務形態に最適なソリューションを選択し、継続的な改善を図ることが重要です。
また、法令や運用指針は随時更新される可能性があります。警察庁や国土交通省の正式な情報を定期的に確認し、最新の要求事項に対応してください。


