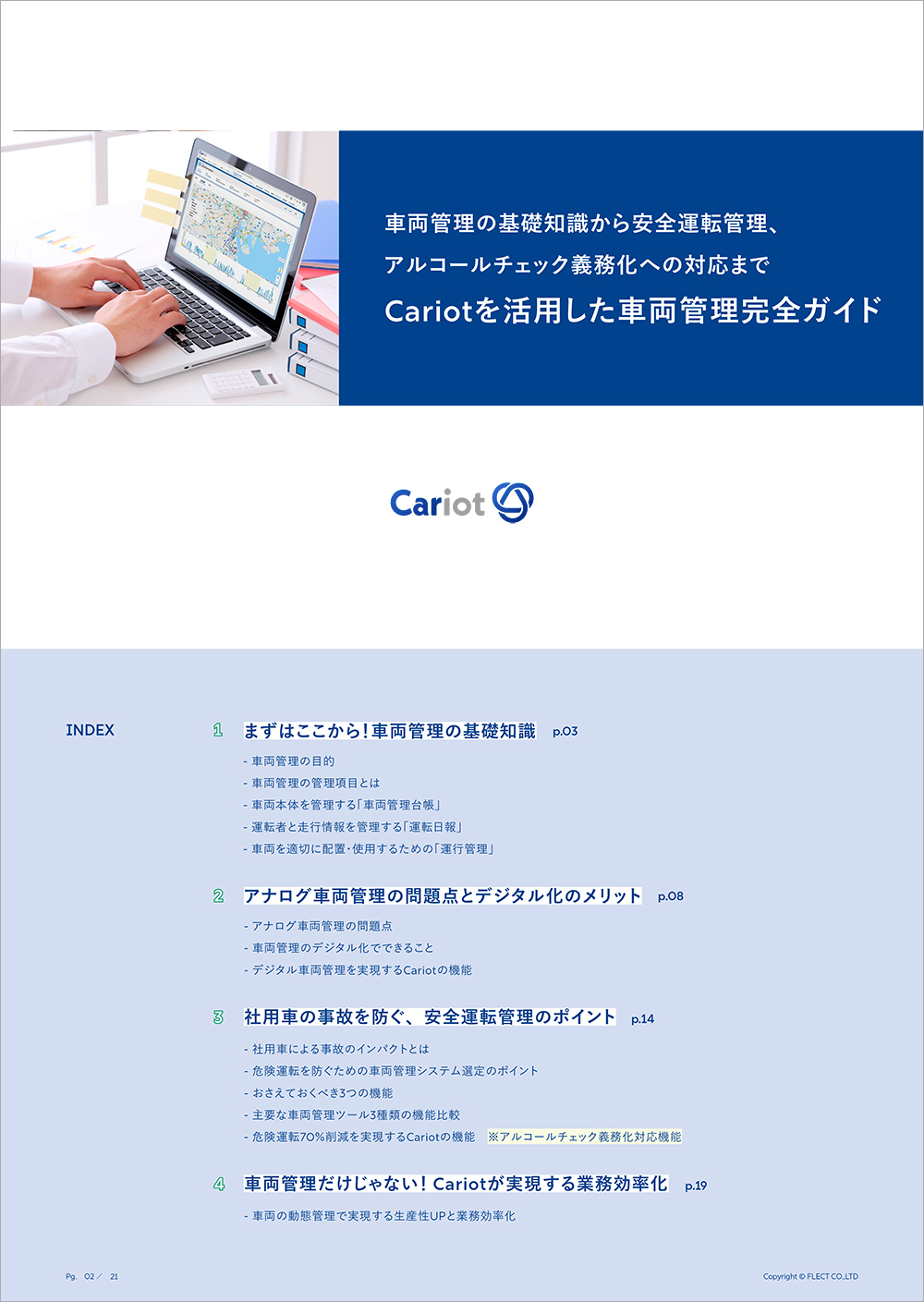企業の安全運転管理者講習は義務?基礎知識から安全運転講習との違いを解説

Cariotを活用した車両管理完全ガイド
「車両管理とは」という基礎知識から社用車事故を防ぐ安全運転のポイントまでを解説しています。これから車両管理をはじめる方や、もっと効率的な管理体制を整えたいご担当者におすすめの資料です。
無料でダウンロード
こんにちは。Cariot(キャリオット)ブログ編集部です。
安全運転管理者講習と安全運転講習は、どちらも交通安全に関連する講習ですが、その目的や対象者が異なります。
この記事では、それぞれの役割や法的な位置付けなどをご紹介します。
安全運転管理業務にお役立ていただければ幸いです。
1.安全運転管理者講習と安全運転講習の違い
安全運転管理者講習と安全運転講習は、どちらも交通安全に関連する講習ですが、その目的や対象者が異なります。
安全運転管理者講習は、企業が法的に受講義務を負うもので、安全運転管理者や副安全運転管理者が受講します。
一方、安全運転講習は任意で実施されるもので、従業員全員が対象となる場合が多いです。
それぞれの講習は、交通安全の向上を目指す点では共通していますが、法的な位置づけや受講の必要性が大きく異なります。
「安全運転管理者講習」は受講義務がある
安全運転管理者講習は、道路交通法に基づいて実施される法定講習です。
一定台数以上の自動車を所有する企業は、使用の本拠ごとに、安全運転管理者を選任し、その管理者が講習を受講する法的義務があります。
この講習は、企業が交通安全を確保するための重要な取り組みであり、受講しなかった場合には罰則が科されることもあります。
「安全運転講習」は任意で実施
安全運転講習は、企業や団体が任意で実施するものです。
従業員の安全運転意識を高め、交通事故を未然に防ぐことを目的としています。
受講は義務ではありませんが、従業員の安全を確保し、企業のリスク管理を強化するために有効な取り組みです。特に、運転業務が多い企業では、安全運転講習を定期的に実施することで、事故防止に役立てることができます。
2.安全運転管理者講習とは
安全運転管理者講習は、企業が交通安全を推進するために重要な役割を果たします。
ここでは、講習の内容や対象者、受講の流れなどを詳しく解説します。
安全運転管理者とその役割
白ナンバーの自動車を使用する企業において、乗車定員が11人以上の自動車にあっては1台、その他の自動車にあっては5台以上を使用している事業所(自動車使用の本拠)ごとに安全運転管理者1名を選任する必要があります。
さらに、20台以上の場合は副安全運転管理者も必要となり、これは20台ごとに1人の追加選任が必要となります。
選任した時は、選任した日から15日以内に都道府県公安委員会に届け出をする義務があるので注意が必要です。必要であるにもかかわらず、選任しなかった場合は、50万円以下の罰金となります。
安全運転管理者の業務は、運転者の適正等の把握、運行計画の作成、点呼と日常点検、酒気帯びの有無の確認、運転日誌の備え付けなど、多岐にわたります。内容は変更されることもありますので、必ず最新の情報を確認しましょう。
参考:安全運転管理者等の資格要件
内閣府令で定める安全運転管理者の業務(道路交通法施行規則第9条の10)
法定講習で1年に1度は受けなければいけない
安全運転管理者講習は道路交通法に基づく法定講習であり、安全運転管理者が原則として1年に1度受講する必要があります。
講習の内容は、交通安全に関する最新の知識や法令、事故防止のための具体的な対策などが含まれます。
企業は、安全運転管理者が確実に講習を受講できるよう、スケジュールを調整する必要があります。
安全運転管理者講習の手数料
安全運転管理者講習の手数料は、実施主体によって異なりますが、一般的には数千円から1万円程度です。
講習の内容や時間、開催場所によっても費用が変動することがあります。
企業は、講習の手数料を予算に組み込み、計画的に受講を進めることが求められます。
安全運転管理者講習受講に必要なもの
安全運転管理者講習を受講する際には、いくつかの書類や物品が必要です。
具体的には、受講申込書、身分証明書、筆記用具などが挙げられます。
また、企業によっては、社内の手続きに必要な書類を準備する必要がある場合もあります。
事前に必要なものを確認し、忘れ物がないように準備しましょう。
安全運転管理者講習の所要時間
安全運転管理者講習の所要時間は、道路交通法施行規則に基づいて定められています。
安全運転管理者講習は6時間以上10時間以下、副安全運転管理者講習は4時間以上8時間以下となっています。
講習の時間は、実施主体や内容によって異なるため、事前に確認することが重要です。
3.安全運転管理者講習を受講する流れ
安全運転管理者講習の受講は、以下のような流れになります。
- 安全運転管理者を選任し、公安委員会へ届け出をする
- 公安委員会から講習のお知らせ、講習手数料の納付書、講習申請書、返信用封筒が届く
- 講習手数料を納入し、講習手数料の領収書コピー、講習申請書を期限までに返送する
- 講習受講日、受講方法が通知される
- 指定された日程で受講する
講習終了後は、受講証明書を受け取り、企業内で適切に管理します。
安全運転管理者講習を受ける際の注意点
安全運転管理者講習を受ける際には、いくつかの注意点があります。
まず、講習の開催日時や場所を事前に確認し、スケジュールを調整することが重要です。スケジュールは、警視庁のHPで公開されるので、早めに確認をしておきましょう。
講習はオンライン講習と会場講習を選択することができます。会場受講の場合は、安全運転管理者証などの必要な書類がありますので、公安委員会からのお知らせはよく確認しておきましょう。
また、代理受講や途中退席もできないのでくれぐれも気をつけましょう。
4.安全運転講習とは
安全運転講習は、企業や団体が任意で実施する交通安全教育です。
ここでは、講習の目的や内容について詳しく解説します。
安全運転講習は任意で受講できる
安全運転講習は、企業や団体が任意で実施するもので、受講は義務ではありません。
しかし、従業員の安全運転意識を高め、交通事故を未然に防ぐために有効な取り組みです。
特に、運転業務が多い企業では、定期的に安全運転講習を実施することが推奨されます。
安全運転講習の目的
安全運転講習の主な目的は、従業員の安全運転意識を高め、交通事故を防止することです。
講習では、最新の交通ルールや事故防止のための具体的な対策、また、そのための知識や技術を学びます。運転中のリスクや事故発生時の対応方法についても解説されます。
安全運転講習の内容
安全運転講習の内容は、交通安全に関する知識や実践的な対策が中心のようです。
講習では、最新の交通ルールや事故事例を学び、安全運転のための具体的な方法を身につけます。
安全運転管理者の業務として、運転者への安全運転の指導が必要なので、その一環として受講するのもよいでしょう。
5.安全運転講習を受けるメリット
安全運転講習を受講するためには、いくつかの方法があります。
企業が独自に講習を実施する場合や、外部の専門機関に委託する場合などが挙げられます。
また、オンラインでの講習を提供している機関もあるので、従業員のスケジュールに合わせて柔軟に受講することが可能です。
安全運転講習を受けることは、企業や従業員にとって多くのメリットがあります。
ここでは、その具体的なメリットについて詳しく解説します。
安全運転を促し、事故の発生を防止できる
講習では、最新の交通ルールや事故防止のための具体的な対策を学ぶため、従業員の安全運転意識が高まります。
これにより、、交通事故の発生を未然に防ぐことが可能です。
企業にとっての損失を防止できる
安全運転講習を受講することで、企業にとっての経済的損失を防止することができます。
交通事故が発生した場合、賠償金や保険料の上昇、業務の停滞など、さまざまな損失が生じます。
安全運転講習を実施することで、これらのリスクを軽減し、企業の経営を安定させることができるでしょう。
企業のイメージ向上につながる
安全運転講習を実施することで、企業の社会的評価が向上します。
従業員の安全を重視し、交通事故防止に積極的に取り組む企業は、社会的に信頼される存在です。
これにより、企業のイメージが向上し、顧客や取引先からの信頼を得ることができます。
6.交通事故によるリスク
交通事故が発生した場合、企業や従業員にとってさまざまなリスクが生じます。
ここでは、その具体的なリスクについて詳しく解説します。
賠償金や保険料の上昇などの経済的損失
交通事故が発生した場合、賠償金や保険料の上昇など、経済的な損失が生じます。
特に、重大な事故が発生した場合には、多額の賠償金や修理費が発生する可能性があります。
また、事故の頻度が高い企業は、保険料が上昇するリスクもあります。
人的・物的損失
交通事故が発生した場合、従業員の負傷や死亡、車両の損傷など、人的・物的な損失が生じます。
これにより、業務の停滞や生産性の低下が発生し、企業の経営に大きな影響を与える可能性があります。
イメージダウン
交通事故が発生した場合、企業の社会的評価が低下するリスクがあります。
特に、事故の原因が企業の安全管理の不備にある場合、顧客や取引先からの信頼を失う可能性があります。
これにより、企業のイメージがダウンし、業績に悪影響を及ぼすことがあります。
7.車両管理システムを使って安全運転促進
車両管理システムを活用することで、企業の安全運転促進を図ることができます。
ここでは、車両管理システムの機能やメリットについて詳しく解説します。
安全運転サポート機能が充実
車両管理システムには、安全運転をサポートする機能が充実しているものが多くあります。
例えば、運転中の急加速や急ブレーキを検知し、運転者に注意を促す機能があれば、運転者の安全運転意識が高まることを期待できます。
事故が起きてからではなく、常日頃から安全運転を心がけることが大切です。
車両管理システムは業務効率化も可能
車両管理システムを活用することで、企業の業務効率化を図ることができます。
例えば、車両の位置情報や走行データをリアルタイムで確認できるものなら、車両の運用管理が効率的に行えるでしょう。
また、車両のメンテナンススケジュールを自動で管理する機能があれば、メンテナンス忘れ防止にもなり、とても便利です。
走行データを使って効果的な安全運転指導も
車両管理システムを活用することで、走行データを基にした効果的な安全運転指導が可能です。
例えば、運転者の運転傾向を分析し、個々に合わせた指導を行うことができます。
これにより、従業員の安全運転スキルが向上し、事故の発生を未然に防ぐことができます。
8.まとめ
安全運転管理者講習と安全運転講習は、企業が交通安全を確保するために重要な取り組みです。
安全運転管理者講習は法的な義務であり、企業は確実に受講する必要があります。
一方、安全運転講習は任意で実施されるものですが、従業員の安全を確保し、企業のリスク管理を強化するために有効です。
また、車両管理システムを活用することで、安全運転促進と業務効率化を同時に図ることができます。車両管理システムにはさまざまな機能を備えているものが数多くありますので、自社に必要な機能は何か、導入する目的は何かを、よく検討しましょう。
企業は、これらの取り組みを積極的に導入し、交通安全の向上に努めることが求められています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
ご意見・ご質問・ご感想・ご要望などがございましたら、下記フォームよりお気軽にお問い合わせください!
※本記事は、一般的な情報を提供することを目的としており、法律的な助言を行うものではありません。参考にする場合は必ず最新の情報をご確認ください。また、本記事の内容についての保証はいたしかねます。本記事の利用により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。